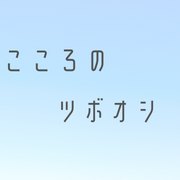- ホーム
- ブログ 気持ちを受け止める
ブログ
ない!ナイ!な〜い!
2021/08/16
今月のメルマガ「読むツボオシ」にも書きましたが、私たちは、「ある」より「ない」に意識が向きがちです。
よくあるコップに入ったお水の例。
コップにお水が半分入っています。半分も入っている!!!と思うのか、半分しか入っていない!!!と思うのか。
前者は「満足」「幸せ」がベースにあり、後者は「不足」や「不満」がベースにあります。
特にいい子ちゃんできた方は、自分が設定している、幸せを感じる、満足するラインやレベルが高くなりがちです。
自分の理想像が高く、そこに達していない自分はまだまだ。
他の人と比べてまだまだ。
こんな私ではだめだめ。
自分に対して、「不足」や「不満」を感じやすいのです。
私もそうでした。今もその傾向は少しあります(笑)
自分の悩みや自分自身をどうにかしたくて、セラピージプシー、ヒーリングジプシー、セミナージプシーしておりました。
自分の外から何かを加えなくてはいけない、誰かの手を借りなくててはいけない、このままではどうしようもない。
本当にナイナイ病でした。求めていた「何か」は外側ではなく自分の内側にあると気づいたのはほんの数年前です。
本当に時間とお金をたくさん使いました。
今振り返ればもう少し近道したかったかなとも思うのですが、この経験があったからこそ、自分の内側に目を向けることができたのです。
他の人にやってもらうのもいいけれど、自分でできたらめっちゃいいやん!と思いEFT-Japanの扉をたたいたのが私のセルフケアの始まりです。
そしてキネシオロジーとの出会いがあり、今に至ります。
私自身、今も自分に対して、「不足」や「不安」がなくなったわけではありません。
でも「不足」や「不安」を感じている自分を否定したり、責めたりすることはなくなり、そんな自分を受け入れることができるようになりました。
そして前より「満足」や「幸せ」を感じれるようになっていきました。
私のように、〇〇ジプシーをやり尽くして、もうどうにかしたい!となってからでもいいですが、できれば皆さんには近道を選んでいただきたいなと思います。
こころのツボオシ講座や個別相談ではそんな私の経験談もお伝えしながら、セルフケアの方法を身につけていただきます。
ない!ナイ!な〜い!から抜け出したい方は是非♪
感情はいつでも出せるし、受けとめることができる
2021/07/19
2歳ぐらいの子どもがえ〜ん、え〜んと目の前で泣いていたら、あなたはまず何て声をかけますか?
小さなお子様がいる方は、その子が目の前で泣いている姿をイメージしてみてください。
大概の方が、「どうしたの?」とか「何があったの?」とか、こちらからその子の状況や状態を確認するかと思います。
次に8歳ぐらいの子どもが、お茶碗をひっくり返しそれが割れてしまってものすごくびっくりして泣いていたとします。
その時、あなたは何て声をかけますか?
「あ〜、もう!何してるの!」「危ないから気をつけて!」「お皿割れちゃった〜」
などど言ってしまいがちではないですか?
2歳ぐらいだとまだ自分の気持ちをうまく言葉に表すことは難しいですよね。
8歳ぐらいになると色々わかってくるし、物事の分別もある程度ついている。
大人の私たちはそう判断します。
2歳の子も8歳の子も同じようにびっくりして怖くて泣いているのに、大人の対応が違ってくるのです。
何故そうなるのか?
それは私たち大人も子どもの頃、きっと親に同じような対応をされている可能性が高いのです。そしてその親もまた同じよう親にそうされてきた。
それは当たり前のように連鎖していきます。
私たちは皆、赤ちゃんでした。おぎゃーとこの世に誕生した時、全力で全身で気持ちを表現していました。
なぜなら言葉が話せないから。
周りの人に自分の快、不快を伝えることに必死でした。
周りの大人も赤ちゃんや小さい子の気持ちを理解するために全力で耳を傾けていました。
ところが成長するにつれて、言葉で色々と話せる、気持ちを伝えられるようになってきます。
すると周りの大人も、その子の言葉や態度で受け取る姿勢になっていきます。
更に、このぐらいならこれぐらいできるだろう、このぐらいわかるだろうと世間や一般的な基準、常識に当てはめて見るようになります。
8歳の子はただただびっくりして怖かった気持ちを受け止めてほしいだけなのに、やってしまった行動を注意されたり、行動に対して親の気持ちをぶつけられたりします。
そうなると、この子の感情は置き去りになったまま、親に怒られないように、次は注意しよう、気をつけようと行動に意識が向いていきます。
行動に意識が向くことは悪いことではありません。学習していく必要はありますから。
でも感情を置き去りにして行動を優先していくと、その置き去りにされた感情が後々色々な形で顔を出してきます。
私のこの感情、どうにかして、気づいて!とからだに症状として現れたり、もやもやや違和感として残り、やる気が出ない、行動できないという状態に繋がったり。
いい子ちゃんで生きてきた方はよりこの傾向が強いかもしれないですね。
お子様がいる方は、まずはその子の気持ちを受け止めてあげてください。
「びっくりしたね〜、怖かったね〜。」と。その後に「危ないから気をつけてね。お皿割れちゃったね。」と行動に対して親としての気持ちを伝えてみてください。
置き去りにしたまま大人になってしまった方は、小さい自分に対して、その時受け止めてもらえなかった気持ちを、大人になった自分が受け止めてあげてください。
その時親からかけてもらいたかった言葉をおとなになったあなたがかけてみてください。
きっと気持ちがこころが軽くなっていくはずです。
ひとりでやるのが難しいと感じる方は、こころのツボオシ講座や個別相談をご利用くださいね。
関連エントリー
-
 敢えて休む、止まる
4月から今まで投稿もせず、SNSも見ずをやっていました。 今までやったことないから 最初数日間はソワソワしてい
敢えて休む、止まる
4月から今まで投稿もせず、SNSも見ずをやっていました。 今までやったことないから 最初数日間はソワソワしてい
-
 楽しみだけど、こわい。。
昨日継続コースを受けることを決めてくださったお客様。「楽しみだけどこわくなってきた」とぽろっと
楽しみだけど、こわい。。
昨日継続コースを受けることを決めてくださったお客様。「楽しみだけどこわくなってきた」とぽろっと
-
 デジタルデトックスをしてから
息子とお散歩しながらお花が綺麗だね〜って立ち止まって一緒に見て、香りを楽しんだり。砂時計の砂が落ちるのをじ
デジタルデトックスをしてから
息子とお散歩しながらお花が綺麗だね〜って立ち止まって一緒に見て、香りを楽しんだり。砂時計の砂が落ちるのをじ
-
 他者目線
自分のビリーフ(思い込み)は自分では気づきにくいのと同じぐらい自分の長所や魅力なんかも気づきにくいん
他者目線
自分のビリーフ(思い込み)は自分では気づきにくいのと同じぐらい自分の長所や魅力なんかも気づきにくいん
-
 私もビックリ!!な展開です
1月に公式LINEプレゼントセッションに来てくださり、そこからhappyコネクト体験セッションを受けてくだ
私もビックリ!!な展開です
1月に公式LINEプレゼントセッションに来てくださり、そこからhappyコネクト体験セッションを受けてくだ